1996年11月・日本教育工学会第12回大会発表論文集P.613
WWWを介した教育向けコンテントの情報発信
A study of Information Sending of Educational Contents with World Wide Web豊福 晋平 TOYOFUKU, Shimpei
国際大学グローバルコミュニケーションセンター
Center for Global Communications, International University of Japan
<あらまし>「キッズページ」は、K-12の児童生徒、保護者、および教育関係者を対象としたウェブページである。本稿では、「キッズページ」運営のコンセプトについて述べるとともに、システム・内容構成、および課題点を報告するものである。
<キーワード> インターネット WWW 教育リソース
1:はじめに
キッズページは1995年2月にスタートした教育向けウェブページであり、主に幼稚園から中学生までの子供達と保護者、教育関係者をターゲットとしている。
開設当初は、学校間交流プロジェクト「メディアキッズ」の紹介を兼ねたものであったが、インターネット上には、日本語の教育向けコンテント、HTML記述のガイドなど必要なリソースがほとんどなく、メディアキッズ参加校から寄せられた作品掲載、学校紹介、実践紹介を間接的に引き受ける形で運営してきた。
96年4月より「メディアキッズ」ホームページの開設により、キッズページは新たに独立したプロジェクトとして再出発し現在に至っている。
(URL=http://www.i-learn.jp/)
2:キッズページのコンセプト
キッズページは教育向けサイトだが、授業実践のための教材リソース提供を目的としたものではない。ページのコンセプトは、大きく次の3つが挙げられる。
1つめは「子供達の自律したネットワーキングを支援すること」である。インターネットアクセスを行う児童生徒は着実に増加している。しかも寄せられるメールから推測すると、大半は家庭からのアクセスである。インターネットは子供達にとって決して安全な場所ではないが、遠ざけておくばかりでは、自ら判断し行動する能力は身に付かない。キッズページでは、これからインターネットへ参加しようとしている子供達と保護者へのガイドを用意し、同年代の子供達が相互にコンタクトできる「場」を提供することを目的としている。
2つめは「ウェブページを子供達のための図書館にすること」である。キッズページでは、大人の作った子供向けコンテントとともに、子供達の作品やレポートがまとめられたページを最重要視している。これらのページを積極的に発掘することで、同世代のコンテンツが同世代に影響を与えあう構造を作りたいと願っている。
3つめは「学校ネットワークを設計運用する教員・教育関係者に有益なリソースを提供すること」である。授業実践そのものよりはもっと基礎的な運用体制づくりに焦点をあて、特に学校ウェブサイトの組立て、運営に関する情報を提供する。
3:サーバシステム構成
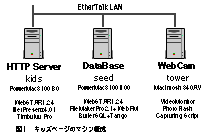
学校でのサーバ構築が容易に行えることを前提に、「キッズページ」ではすべてMacintoshベースでシステムを構成している(図1)。WWWサーバアプリケーションのWebSTARほか、FTPサーバ、データベースエンジン、ライブ映像を5分おきにキャプチャ・中継する機能、サーバ稼働監視プログラムなどを3台に分散させている。
サーバコンテントのメンテナンスは、主にAppleTalkによるリモートマウントがFTPを用いる。数の多い学校URLリストは、FileMakerProとExcelで管理し、スクリプト制御によるオートパイロットで特定サイトの情報を監視と、差分抽出を行っている。
4:キッズページの利用状況
一日当たりのヒット数は7000〜10000件で斬増傾向にある。キッズ向けに寄せられるメール(kidsmail@glocom.ac.jp)はアンケートをのぞけば一日4〜6通である。
5:キッズページの掲載情報
キッズページは、子供向け「キッズのページ」教育サポート向け「教育の森」英語版の「English Info」の3つの入口を持っている。
「学校サイト検索」(/schools/)は、国内の幼稚園〜高等学校(含む高等専門学校、各種特殊諸学校)のウェブページ・学校紹介のリストである。平成8年8月現在853校の登録がある。特に平成8年に入ってからの増加数は著しい。リスト中には正式公開ではないものも含まれるが、これらは教員や卒業生が個人的に作っているもの、PTAが立ち上げたものなど多彩である。学校ウェブが学校紹介や教材提供のみならず、様々な関係者のコンタクトにも利用され始めている証であろう。
「このゆびとまれ」(/lab/)は、共同研究、アンケート、文通の呼びかけを扱うページである。投稿数は少ないが、最近は海外からの文通申し込みが目立つ。
「ミュージアム」(/museum/)「ライブラリ」(lab/libindex.html/)は子供達のための図書館を目指したものであり、テーマ別に子供達の作った作品と、大人の作ったコンテントを区別して掲載している。
6:課題点

WWWによる情報発信は、1:コンテントそのものの掲載 2:情報の再編集(リンクリスト)が基本であり、しかも、ある程度の頻度で更新が行われなければならない。これらコンテント系の編集は雑誌編集と同じ労力を要し、個人ベースでの運営は相当な負担となっている。継続的なメンテナンスには、積極的な自動化やデータベースの応用などが必要とされる。
WWWでの発展的な捉えとしては、3:電子掲示板(呼びかけ、コンタクトのきっかけづくり)、4:ユーザー参加型コンテントが挙げられる。キッズページには現在この形のページは存在しないが、サーバプログラムの拡張として、どのようにインタラクティブな仕掛けを作るかが課題となるだろう。
また、教育向けページ、学校ウェブの爆発的な数の増加は「どこのページを見たらよいか分からない」という状況を作り出している。こと学校ウェブに関しては、これから立ち上げを行う学校サイドに「良いページ」の基準を示すうえでも、ランク付けや評価を行う必要性がある、と思われる。
Jun. 23. 1998.
Copyright (C)1996 Center for Global Communications, International University of Japan